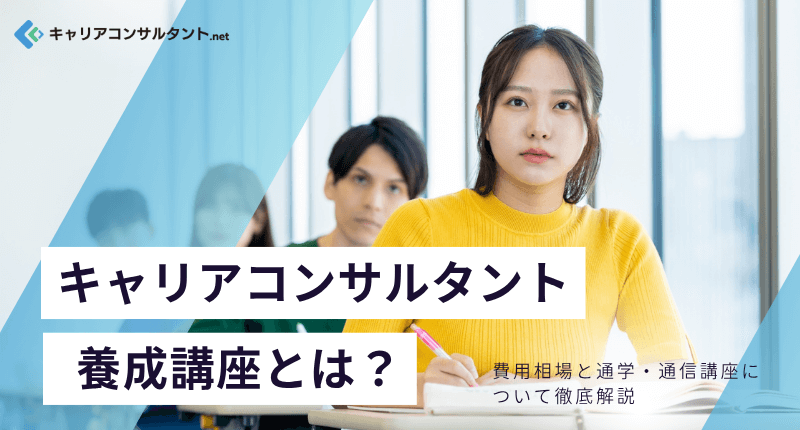
- キャリアコンサルタントとは?
- > キャリアコンサルタント養成講座とは?費用相場と通学・通信講座について徹底解説
キャリアコンサルタント養成講座とは?費用相場と通学・通信講座について徹底解説
更新日: 2025/11/05
「このまま今の仕事を続けていていいのかな」そんな迷いを抱く人が増えています。
キャリアコンサルタントは、働く人の人生に寄り添い、道を一緒に見つけていく国家資格です。
キャリア支援の専門家、国家資格キャリアコンサルタントを取得するための第一歩となるのが「キャリアコンサルタント養成講座」です。
ただ、講座の数が多く、費用や通学・通信の違い、給付金の条件など、調べるほどに悩んでしまう人も少なくありません。
この記事では、キャリアコンサルタント養成講座についてわかりやすく整理しています。
自分に合った講座を見極めるための基準についても具体的に解説します。
\講座を比較して選ぼう!/
キャリアコンサルタントの講座を資料請求(無料)キャリアコンサルタント養成講座とは?受講の流れと修了条件
キャリアコンサルタント養成講座は、国家資格「キャリアコンサルタント」の受験資格を得るための手段のひとつです。キャリアコンサルタント試験合格者の約9割は受験資格が「養成講習修了」である公式データ※もあります。
出店:第29回キャリアコンサルタント試験 試験結果
この講座では、相談技法や心理学・キャリア理論などの座学に加え、面談演習やケーススタディを通じて実践的スキルも体系的に学びます。したがって、資格取得だけでなく、現場対応力を高めるためにも価値がある講座です。
養成講座は受験資格取得のために必須
結論から言うと、キャリアコンサルタント試験を受けるためのには、厚生労働大臣が認定する「キャリアコンサルタント養成講座」を修了することが主要なルートの一つです。(すべての受験者が必ずしもこれを利用するわけではありません)
この制度は、相談支援として必要な知識・技術を一定水準で担保する意図があります。
- キャリア理論
- 相談技法
- 倫理
- 労働法規など
講座では基礎理論を系統的に学びます。
実技面では、指導者による面接演習・ロールプレイを通じてフィードバックを得る機会が設けられることが多いです。
そのため、試験を視野に入れている段階で、キャリアコンサルタント養成講座の受講を早めに検討するのが現実的な選択肢といえます。
ただし、キャリアコンサルタント養成講座を修了する方法は、あくまで「受験資格を得るための一つの方法」です。実務経験(一定の要件を満たすもの)がある方は、キャリアコンサルタント養成講座を修了しなくても受験できる場合があります。
講座の内容とカリキュラム構成
キャリアコンサルタント養成講座のカリキュラムは、理論・実践・自己理解の3領域で構成されています。
キャリア相談に必要な知識・倫理・対人支援スキルを体系的に身につけることを目的としており、厚生労働省が示すモデルカリキュラムに基づいて設計されています。
| 区分 | 主な内容 | 学習目的 |
| 理論分野 | キャリア発達理論、心理学、労働法規 | 理論的な支援の基盤を理解する |
| 実践分野 | 面談演習、ロールプレイ、ケース検討 | 対人支援スキルを実践的に習得する |
| 自己理解 | キャリアプラン設計、自己分析 | 自身の相談姿勢を確立する |
このように、理論で枠組みを学び、演習で実践力を高める流れが特徴です。
特に面談ロールプレイでは、講師や指導者から具体的なフィードバックを受けながら、自分の強みや課題を客観的に把握できます。
「知識を学ぶ」だけでなく、「相談者の話を聴き、支え、問い、整理する」スキルを磨くことで、試験合格に必要な力と、現場で活きる支援力の両方を養えます。
修了要件と受講期間の目安
キャリアコンサルタント養成講座を修了するには、出席・課題・評価の3つを満たすことが求められます。
厚生労働省の認定要領では統一基準は設けられていませんが、多くの講座では次のような要件を定めています。
- 出席率: 全カリキュラムの 70〜80%以上(講座により異なる)
- 課題提出: 理論・実技に関するレポートや小テストの合格
- 実技評価: 面談ロールプレイやケース検討を通じた到達度確認
これらを総合的に満たした場合に「修了」と認定され、修了証明書が発行されます。
この修了証明書は、国家試験の受験資格を得るための要件のひとつです。別途、指定期間内に受験申請をおこなうことで国家試験に出願できます。
\講座を比較して選ぼう!/
キャリアコンサルタントの講座を資料請求(無料)キャリアコンサルタント養成講座の費用と相場
キャリアコンサルタント養成講座は、国家資格取得への第一歩となる重要なステップです。
ここでは、受講料の相場や通信・通学の形式による費用の違い、さらに分割払いや教育訓練給付金制度を活用して費用負担を軽減する方法について解説します。
受講料の相場と費用
キャリアコンサルタント養成講座全体にかかる費用は、受講料だけでなく、教材費・試験料・登録費・更新費用なども含めて見積もる必要があります。
多くのキャリアコンサルタント養成機関の情報を総合すると、実質的な総額は約34万〜60万円前後が目安となることが多いです。
| 項目 | 範囲(目安・税込) |
| 養成講座受講料 | 約198,000〜437,800円(講座によってはこの範囲外も) |
| 教材費・副教材 | 数千円〜数万円 |
| 試験料 | 38,800円(学科 8,900円 + 実技 29,900円) |
| 登録料・登録免許税・手数料 | おおよそ 17,000円(登録免許税 9,000円+登録手数料 8,000円、諸団体情報に基づく) |
| 試験対策補講・模擬試験 | 数千円〜数万円 |
| 更新料・更新講習 | 数千円〜数万円(都度発生) |
働きながら受講する人には、通信型・オンライン併用型を選ぶことで通学コストを抑えられます。
一方で、現場での実践力を重視したい人は通学・演習重視型を選ぶなど、自分の学び方と目的のバランスを見据えて判断することが、費用対効果を最大化する鍵となります。
通信・通学で費用
結論から言うと、キャリアコンサルタント養成講座の受講料はおおむね30万〜50万円前後が相場です。
講座によって費用に幅があるのは、学習形式・講師陣・実技演習の充実度・サポート体制など、提供内容に大きな違いがあるためです。
| 形式 | 受講料の相場目安 |
| 通信講座 | 約25万〜35万円 |
| 通学講座 | 約40万〜55万円 |
| 通信+通学講座 | 約35万〜50万円 |
さらに、専門実践教育訓練給付金制度の対象講座であれば、最大で受講料の50%(上限56万円)まで支給されます。
その場合、たとえば受講料が45万円の講座なら、実質負担は約22万円程度まで下がるケースもあります。
- 実技サポート(面談練習・講師フィードバック)
- 給付金対象かどうか
- 修了後の就職・登録支援の有無
価格だけで判断せず、学習後のフォロー体制まで含めて比較検討することが重要です。
分割払い・給付金で費用を抑える方法
受講料の負担を軽減するには、分割払い制度や教育訓練給付金制度を上手に活用するのが効果的です。
分割払いを利用すれば、初期費用を抑えながら毎月一定額で受講できるため、まとまった支出を避けられます。
また、厚生労働省の「専門実践教育訓練給付金」を利用すれば、条件を満たした場合に受講料の最大70%(上限112万円)が支給されます。
- 修了時に受講料の50%(上限56万円)
- 資格取得・就職など一定条件を満たした場合に追加で20%(上限28万円)
これにより、実質的な自己負担を半分以下に抑えることも可能です。
\講座を比較して選ぼう!/
キャリアコンサルタントの講座を資料請求(無料)教育訓練給付金の対象講座と申請の流れ
キャリアコンサルタント養成講座は、「専門実践教育訓練給付金」の対象となるケースが多く、一定の条件を満たせば、受講料の最大70%(上限112万円)が支給されます。
ここでは、その対象講座の確認方法と、申請から給付金を受け取るまでの流れを解説します。
対象となる講座と確認方法
結論として、教育訓練給付金の対象となるのは、厚生労働大臣が指定した「専門実践教育訓練講座」に限られます。
この制度は、国が「就職・転職・キャリア形成に効果が高い」と認めた講座を対象に支援をおこなう仕組みです。
指定には、講座時間・教育内容・就職実績・講師体制などに関する厳格な基準が設けられています。
対象講座かどうかを確認するには、以下の方法があります。
| 確認方法 | 内容 |
| 厚生労働省公式サイト | 教育訓練給付制度 検索システム で講座名やスクール名を検索。最新の指定講座(毎年4月・10月更新)を確認 |
| 各スクールの公式サイト | 講座ページに「専門実践教育訓練給付金 対象講座」と明記されていることを確認。指定番号の掲載があるとより確実。 |
| ハローワーク | 制度の説明や申請手続きの相談を対面で受けられる。初回利用時には「受講開始前」に申請が必要。 |
なお、受講開始前に対象講座かどうかを確認し、申請を済ませておかないと、修了後に申請できない点には注意が必要です。
受講後の申請は制度上認められていないため、必ず受講前に講座の指定状況を確認しておきましょう。
申請から受給までの手順
教育訓練給付金を受け取るためには、受講開始前に必ずハローワークでの手続き(事前申請)が必要です。
この制度は、「あらかじめ対象者として認定された人に対して支給される」仕組みのため、受講開始後の申請は無効になります。
申請から支給までの主な流れは以下のとおりです。
1.事前確認:受講開始1か月前までにハローワークで「受給資格確認申請」
2.受講開始:指定講座で学習を開始。受講料を一旦全額自己負担する
3.講座終了:修了証明書を取得(出席率・成績要件を満たす必要あり)
4.支給申請:修了後1か月以内にハローワークで「支給申請」手続き
5.支給決定:審査を経て、指定口座に給付金が振り込まれる
この手順を正しく踏むことで、修了時に受講料の50%(上限56万円)、さらに資格取得や就職など一定条件を満たすと追加20%(上限28万円)が支給され、合計で最大70%(上限112万円)が支給されます。
- 受講前の「受給資格確認申請」
- 修了後1か月以内の「支給申請」
どちらかが漏れると支給対象外になるため、必ず余裕をもって手続きを行いましょう。
\講座を比較して選ぼう!/
キャリアコンサルタントの講座を資料請求(無料)通学・通信どちらが向いている?学習スタイル別の特徴
キャリアコンサルタント養成講座は、通学、通信+通学、通信+オンラインといった複数の学習形式があります。どれを選ぶかで、費用・学習ペース・サポート体制が大きく変わります。
通学講座のメリット・デメリット
通学講座の最大の魅力は、実技演習や講師との対面指導を通じて、現場で通用するスキルを集中的に磨ける点にあります。
特にキャリアコンサルタント試験ではロールプレイや面談実技の比重が高い※ため、講師から直接フィードバックを受けながら練習できる環境は大きな強みです。
※筆記試験は100点満点、実技試験は論述と面接の合計150点満点短期間(例:3〜6か月)で実践力を身につけたい人には、効率の良い学習形態です。
一方で、受講料が通信講座よりも5〜15万円ほど高くなる傾向があり、通学にかかる時間・交通費の負担も発生します。
社会人の場合は、夜間・週末コースやハイブリッド(通学+オンライン)形式があるかどうかを確認しておくと、両立がしやすくなります。
| 項目 | メリット | デメリット |
| 学び方 | 講師・仲間との直接交流でモチベーションを維持しやすい | 通学時間・交通費が必要 |
| 費用 | 給付金対象なら実質負担を抑えられる | 教材費込みで40〜50万円前後、通信型より高額になりやすい |
| 効果 | 実技・面談スキルの定着が早く、リアルな場面で学べる | 自分のペースで進めにくい、日程調整が必要 |
通学型は、実践力を重視する人・面談経験を積みたい人・講師の直接指導を求める人に特に向いています。
一方で、スケジュールの自由度や費用を優先したい場合は、通信・オンライン型の方が現実的な選択となるでしょう。
通信講座のメリット・デメリット
通信講座の最大の魅力は、働きながらでも自分のペースで学べる柔軟さにあります。
録画講義やオンライン教材を活用することで、通学時間を気にせず学習を進められるため、地方在住者や多忙な社会人にも取り組みやすいのが特徴です。
一方で、学習のモチベーション維持や実技演習の不足が課題となることもあります。
キャリアコンサルタント養成講座では、厚生労働省の指定要件として一部のスクーリング(対面またはオンライン実技指導)が義務付けられており、完全オンラインのみでは修了できません。
| 項目 | メリット | デメリット |
| 費用 | 受講料は25〜35万円前後と比較的安価 | 通学講座に比べて実技サポートが少ない傾向 |
| 学習ペース | 自分の都合で進められ、働きながら学びやすい | モチベーション維持が難しく、計画的な自己管理が必要 |
| サポート | チャット・メール・オンライン面談など、柔軟なサポート体制が整う講座もある | 講師との直接指導や即時フィードバックを受けにくい |
通信型は、時間の制約が大きい社会人や、自律的に学習を進められる人に適しています。
一方で、対人スキルや面談技法を重点的に磨きたい場合は、ハイブリッド型(通信+通学)を選ぶことでバランスを取りやすくなります。
オンライン+通学併用タイプの選択肢
近年では、オンライン学習と通学演習を組み合わせた「ハイブリッド型講座」が広がりを見せています。
理論をオンラインで学び、実技演習を通学(またはオンライン実技)でおこなうことで、柔軟なスケジュール管理と実践的な指導を両立できるのが特徴です。
通学頻度は月1〜2回程度(全体で3〜6日ほど)に抑えられており、講師からの直接指導を受けながら、地方からでもオンラインで理論を学習できます。
| 項目 | 特徴 |
| 学習形態 | オンラインで理論学習、通学で面談演習 |
| メリット | 柔軟なスケジュールを保ちつつ、講師の直接指導やグループ演習を受けられる |
| デメリット | 通信環境の確保や日程調整が必要。通学会場が都市部に限定される場合もある |
| 費用目安 | 約35〜45万円 |
オンライン+通学併用は、仕事・家庭・学習のバランスを取りたい人に特に向いています。
理論と実技を無理なく組み合わせられるため、現在では主流の学習スタイルの一つといえるでしょう。
\講座を比較して選ぼう!/
キャリアコンサルタントの講座を資料請求(無料)キャリアコンサルタント養成講座選びで失敗しない3つのポイント
キャリアコンサルタント養成講座は、どれも似て見えて内容やサポートの質に大きな差があります。
ここでは、受講前に必ず確認しておきたい3つのチェックポイントを紹介します。
1.給付金対象講座か確認する
まず最初に確認すべきなのは、受講を検討している講座が「専門実践教育訓練給付金」の対象になっているかどうかです。
この制度を活用すれば、条件を満たした場合に受講料の最大80%(上限112万円)が支給されます。
- 修了時に50%(上限56万円)
- 資格取得や就職など一定条件を満たすと追加30%(上限28万円)
たとえば受講料が40万円の場合、給付制度を利用すれば実質負担が12〜20万円程度になるケースもあり、経済的な効果は非常に大きいといえます。
対象講座かどうかの確認方法は次のとおりです。
- 厚生労働省公式サイトの教育訓練給付制度検索システムにアクセス
- 「専門実践教育訓練」を選択し、講座名やスクール名を入力
- 対象講座として指定されているかを確認
この指定は年2回(4月・10月)に更新されるため、申し込み時期によって結果が変わる場合もあります。
給付金対象外の講座を選んでしまうと、制度を利用できずに数十万円の差が出ることもあるため、申し込み前に必ず確認しておくことが重要です。
2.欠席・振替対応の柔軟性も確認する
次に確認したいのが、スケジュール変更への対応力です。
社会人の受講者は、仕事・家庭の事情で全日程に参加できないことも多く、欠席時のフォロー体制が修了可否に直結します。
キャリアコンサルタント養成講座では、出席率8割以上が修了要件と定められているため、欠席した場合の「振替受講」「録画視聴」「補講制度」の有無を事前に確認することが重要です。
実際の講座では以下のような対応パターンがあります。
| 対応方法 | 内容 | 注意点 |
| 振替受講 | 別日・別校舎で同内容の授業を受講できる | 座席数に制限があり、早めの予約が必要 |
| 録画視聴 | 授業録画を後日視聴できる(オンライン型中心) | 出席扱いにならない場合もある |
| 補講・個別対応 | 講師や担当者が個別指導を実施 | 有料オプションとなることもある |
特に近年は、オンライン振替(Zoomやオンデマンド)を活用できる講座も増えており、地方在住や多忙な社会人でも継続しやすくなっています。
一方で、講座によっては一部科目の振替が認められず、修了要件を満たせないケースもあるため、申し込み前に「振替・補講対応の範囲」を必ず確認しておきましょう。
柔軟なスケジュール対応がある講座ほど、学習の継続率が高く、結果的に合格・修了までスムーズに進めます。
3.実技サポートの手厚さ
最後に確認すべきなのは、実技サポートの充実度です。
キャリアコンサルタント試験では、学科よりも実技(ロールプレイ・口頭試問)の難易度が高いとされており、この対策が合否を左右する大きな要因になります。
受講前にチェックしておきたい実技サポートのポイントは以下のとおりです。
| 確認項目 | チェック内容の目安 |
| 模擬面談の実施回数 | 2〜3回以上のロールプレイ練習があるか(受講生同士+講師フィードバック) |
| 講師の質 | 現役キャリアコンサルタント、または試験官経験者が指導に関わっているか |
| フィードバックの方法 | 録画・録音を活用した自己分析、個別コメントや添削があるか |
| オンライン実技対応 | Zoomなどでの実技指導・口頭試問練習が可能か |
実技指導が充実している講座では、講師からの個別フィードバックを受けながら繰り返し練習できるため、実践力と自信を着実に高められます。
こうした講座は、結果的に合格率が高い傾向です。
一方で、実技サポートが十分でない場合、知識は理解していても、面談現場での対応力(傾聴・質問・要約・目標設定)が身につかず、実技試験で苦戦するケースもあります。
\講座を比較して選ぼう!/
キャリアコンサルタントの講座を資料請求(無料)まとめ|最適な講座を選んで、キャリア支援のプロへ
キャリアコンサルタント養成講座を選ぶ際は、費用・通いやすさ・サポート体制の3つを総合的に判断することが重要です。
- 給付金対象講座かどうか
- 欠席時のフォロー体制
- 実技指導の充実度
この3点は、講座選びでの失敗を防ぐうえで、見逃せないチェックポイントです。
また、自分の目的が「資格取得」なのか「実務スキルの習得」なのかを明確にしておくと、選ぶべき講座が自然と絞り込まれてきます。
最適な講座を選ぶことは、試験に合格するためだけでなく、相談者の人生に寄り添えるキャリア支援のプロとしての一歩を踏み出すことにもつながります。
自分に合った環境で学ぶことが、長く活かせるスキルと自信を育てる鍵です。
\講座を比較して選ぼう!/
キャリアコンサルタントの講座を資料請求(無料)キャリアコンサルタントの講座選びなら(BrushUP学び)


BrushUP学びはスクールや学校、講座の総合情報サイト。
最安・最短講座や開講日程、分割払いなどをエリアごとに比較して無料でまとめて資料請求できます。
まずは近くのスクールをチェックしてみてくださいね♪
電話での請求も可能です。
\講座を比較して選ぼう!/
キャリアコンサルタントの講座を資料請求(無料)- キャリアコンサルタント試験情報
- キャリアコンサルタント試験 試験内容を徹底解説 キャリアコンサルタント試験の難易度・合格率は? キャリアコンサルタント学科試験とは? キャリアコンサルタント試験の申し込み期間はいつ? キャリアコンサルタント試験の試験日程一覧 キャリアコンサルタント受験資格を徹底比較 キャリアコンサルタント実技試験とは? キャリアコンサルタント論述試験の内容は? キャリアコンサルタント技能検定2級とは? キャリアコンサルタント試験 出題内容・勉強法を徹底解説!
- キャリアコンサルタントを目指す方向けのおすすめ記事
- キャリアコンサルタントの年収は? キャリアコンサルタントの将来性は高い!? キャリアコンサルタントの仕事内容は? キャリアコンサルタント資格とは? キャリアコンサルタントは独学で合格できる? キャリアコンサルタント国家資格とは? キャリアコンサルタントになるには? キャリアコンサルタントの取り方決定版 キャリアコンサルタントの役割とは? キャリアコンサルティングとは? 本当にキャリアコンサルタントの資格は無駄? キャリアコンサルタントは副業にできる? キャリアコンサルタント資格の種類や活かし方
- キャリアコンサルタント養成講座の解説
- キャリアコンサルタント養成講座とは? キャリアコンサルタント養成講座はオンラインでも学べる? キャリアコンサルタント養成講座を辞めたい… キャリアコンサルタント講座のスクール一覧 キャリアコンサルタント養成講座をお得に受けるには? 働きながらキャリアコンサルタントを目指す! 土日開講のキャリアコンサルタント養成講座
- 【エリア別】キャリアコンサルタント養成講座を探す
- 東京都内のおすすめスクール 大阪府のおすすめスクール 北海道のおすすめスクール 愛知県のおすすめスクール 福岡県のおすすめスクール 埼玉県のおすすめスクール 京都府のおすすめスクール 静岡県のおすすめスクール 兵庫県のおすすめスクール 千葉県のおすすめスクール 島根県のおすすめスクール 石川県のおすすめスクール 長野県のおすすめスクール 岐阜県のおすすめスクール 岡山県のおすすめスクール 三重県のおすすめスクール 広島県のおすすめスクール 神奈川県のおすすめスクール 熊本県のおすすめスクール 鹿児島県のおすすめスクール 新潟県のおすすめスクール 香川県のおすすめスクール 岩手県のおすすめスクール 山形県のおすすめスクール 沖縄県のおすすめスクール 福島県のおすすめスクール 山梨県のおすすめスクール 群馬県のおすすめスクール 栃木県のおすすめスクール 茨城県のおすすめスクール 富山県のおすすめスクール 宮城県のおすすめスクール
- 【スクール別】キャリアコンサルタント養成講座を探す
- ヒューマンアカデミーの学校情報 資格の総合スクール LEC(れっく)東京リーガルマインドの学校情報 キャリア開発のパイオニア/日本マンパワーの学校情報 リカレントの学校情報 一般社団法人 日本産業カウンセラー協会の学校情報 一般社団法人 地域連携プラットフォームの学校情報 東海道シグマの学校情報 キャリアカウンセリング協会/GCDF-Japanの学校情報
- キャリアコンサルタント関連資格の記事
- 経営コンサルタント資格は本当に必要?
- キャリアコンサルタントとは?
- > キャリアコンサルタント養成講座とは?費用相場と通学・通信講座について徹底解説