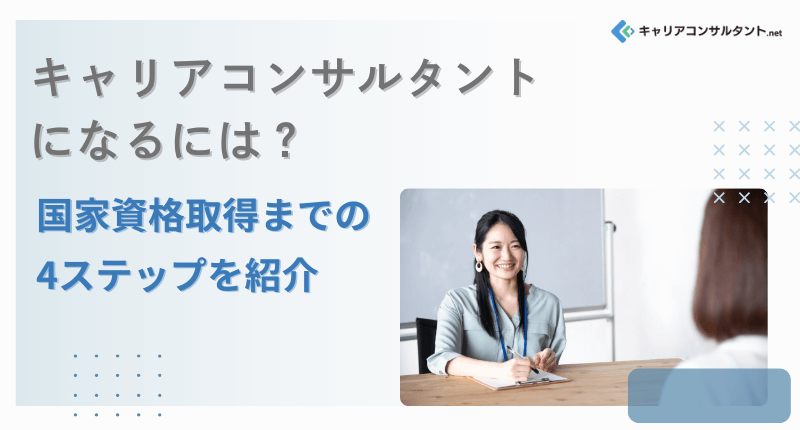
- キャリアコンサルタントとは?
- > キャリアコンサルタントになるには?国家資格取得までの4ステップを紹介
キャリアコンサルタントになるには?国家資格取得までの4ステップを紹介
更新日: 2025/11/28
「この先、誰かのキャリアを支える仕事をしてみたい」と考えたとき、キャリアコンサルタントという資格に行き着く人は多いものです。
国家資格として注目される一方で、「どうすれば取得できるのか」「講座が多くて選べない」と悩む声もよく聞かれます。
この記事では、未経験からキャリアコンサルタント資格を取得するまでの具体的な手順と、講座選びのポイントを解説します。
\講座を比較して選ぼう!/
キャリアコンサルタントの講座を資料請求(無料)キャリアコンサルタントになるには?【資格取得の全ステップ】
キャリアコンサルタントは国家資格であり、取得までには明確なステップを踏む必要があります。ここでは、キャリアコンサルタントになるための最短ルートを詳しく解説します。
STEP1:受験資格と受験ルートを確認する
キャリアコンサルタント試験を受験するには、職業能力開発促進法で定められた受験資格を満たす必要があります。
受験資格には主に3つのルートがあり、自身の経験や状況に応じて最適な方法を選択します。
| ルート | 内容 | 向いている人 | 注意点 |
| 養成講習を修了 | 厚労省認定の養成講習(150時間)を修了する | 未経験者、実務経験が浅い人 | ・最も一般的なルート ・体系的に学べる |
| 実務経験あり | キャリア相談の実務を3年以上経験している | 人材業界や企業人事などで実務経験がある人 | ・1対1の相談業務が必要 ・情報提供や研修運営のみは不可 |
| 技能検定に合格 | 技能検定(1級・2級)の学科または実技に合格している | すでにキャリア相談業をおこなっている人 | ・技能検定自体にも受験資格があるため実務経験者向け |
受験資格を満たしているかどうかは、試験実施機関のWebサイトで詳細な要件を確認できます。
実務経験で受験する場合は、実務経験証明書を勤務先や取引先に作成してもらう必要があります。
証明書には業務内容や期間、相談件数などを具体的に記載し、証明者の署名と押印が必要です。
STEP2:キャリアコンサルタント養成講座を受講・修了する
キャリアコンサルタント養成講習は、厚生労働大臣が認定した団体が実施する150時間の専門講習です。
キャリアコンサルタント養成講習ではキャリアコンサルティングの理論や技法、関連法規、労働市場の知識、倫理などを体系的に学びます。
内容は厚生労働省が定めたカリキュラムに基づいており、どの団体で受講しても学習の基本構成は共通です。
キャリアコンサルタント養成講習のカリキュラムは5つの科目にわかれています。
| 科目 | 学習時間 |
| キャリアコンサルティングの社会的意義 | 2時間 |
| 必要な知識 | 35時間 |
| 必要な技能 | 76時間 |
| 倫理と行動 | 27時間 |
| その他科目 | 10時間 |
講習の約半分は講義形式で構成されキャリア理論や発達理論、カウンセリング理論、労働法規、雇用情勢などを学びます。残りは演習形式で、実技試験(面接・論述)を実践的に身につけます。
STEP3:国家試験を受験・合格する
キャリアコンサルタント国家試験は、学科試験と実技試験の二つで構成されています。試験は年3回実施され、3月、7月、11月に実施されます。
試験実施機関は、キャリアコンサルティング協議会と日本キャリア開発協会の2団体です。
いずれの団体で受験しても国家資格として認められます。
STEP4:キャリアコンサルタントとして登録する
国家試験に合格しただけでは、まだキャリアコンサルタントを名乗れません。
職業能力開発促進法に基づき、キャリアコンサルタント名簿に登録することで、正式な資格保有者として認められます。
登録手続きは特定非営利活動法人キャリアコンサルティング協議会の登録センターでおこないます。
\講座を比較して選ぼう!/
キャリアコンサルタントの講座を資料請求(無料)キャリアコンサルタント試験の内容と難易度
キャリアコンサルタント試験は決して簡単ではありません。なぜなら、キャリアコンサルタント試験は学科試験と実技試験で構成されており、いずれも合格する必要があるからです。
試験内容は幅広い領域から出題されるため、体系的な学習と十分な演習が求められます。ですが、正しい準備をおこなえば社会人でも十分に合格を目指せます。
- キャリア理論
- カウンセリング技法
- 労働法規など
出題範囲が多岐にわたり、知識量と理解力の両方が必要になるためです。合格率は年度によって変動しますが、一定の水準に落ち着いています。講座を活用した受験者は理解の定着や実技対策を進めやすく、未経験者でも十分に合格を狙える資格です。
\講座を比較して選ぼう!/
キャリアコンサルタントの講座を資料請求(無料)キャリアコンサルタント資格を取得した後のキャリアと将来性
キャリアコンサルタント資格は、取得後の働き方が幅広い点が特徴です。企業、教育機関、行政など活躍の場が広がるため、将来的なキャリア形成にもつながります。
ここでは、キャリアコンサルタント資格が活かせる仕事例と平均年収、さらなるステップアップに関して紹介します。
キャリアコンサルタント資格が活かせる仕事例
キャリアコンサルタントの資格は、多様な組織で活用される汎用性の高い国家資格です。
理由はキャリア支援が求められる領域が企業、学校、行政など多岐にわたり、専門性を生かせる業務が安定して存在するためです。具体的な活動領域を比較すると、次のようになります。
| 活動領域 | 主な業務内容 |
| 企業 | ・社員面談 ・研修企画 ・組織開発 |
| 学校 | ・進路相談 ・就職支援 ・キャリア教育 |
| 行政 | ・求職者支援 ・職業訓練関連業務 |
| 独立 | ・個人相談 ・研修講師 ・キャリア支援サービス |
企業では社員のキャリア面談や研修企画に携わり、教育機関では学生の進路相談や就職支援を担当します。行政では職業訓練や求職者支援の窓口業務に従事するケースがあります。独立した場合は、個人向けコーチングや企業研修の講師として活動する働き方が中心です。
幅広い選択肢をもてることで、自分の関心や働き方に合わせてキャリアを形成しやすくなります。
キャリアコンサルタントの平均年収と働き方
キャリアコンサルタントの平均年収は勤務形態によって大きく異なります。各種調査では、キャリアコンサルタント全体の平均年収は300万円から600万円程度が中心とされています。
| 活動領域 | 雇用形態 | 年収目安 | 特徴 |
| 企業(人事・研修部門) | 正社員 | 400万円〜600万円(管理職で600万円以上も) | 給与が安定し、昇給や役職アップが見込める |
| 大学・専門学校・公的機関 | 非常勤・契約職員 | 200万円〜400万円 | 勤務形態は柔軟だが、年収は控えめ |
| フリーランス・独立 | 個人事業・業務委託 | 100万円〜800万円(実績次第で1000万円以上も) | 収入の変動幅が大きく、働き方の自由度が高い |
複数の現場や業務を組み合わせて働くケースが多く、希望に応じて柔軟に収入を設計できる点が特徴です。
さらなるステップアップ(2級・1級技能士など)
キャリアコンサルタントとして経験を積むと、2級や1級キャリアコンサルティング技能士を目指す選択肢が生まれます。
技能士資格は国家検定として位置付けられており、より高度な相談支援能力や指導力を証明できます。
- - 2級:個別相談における高度な対応能力が求められる
- - 1級:組織全体のキャリア支援を設計する力や教育・指導スキルが問われる
技能士資格を取得すると職場での役割が広がり、研修講師や指導者として活躍する場面が増えます。
長期的にキャリア支援の専門性を高めたい人にとって、技能士資格は必要な資格です。
\講座を比較して選ぼう!/
キャリアコンサルタントの講座を資料請求(無料)キャリアコンサルタント養成講座の選び方
キャリアコンサルタントの資格取得を目指すうえで、養成講座選びは重要な過程になります。ここでは、自分に適した講座を判断するための視点を整理します。
費用・給付金制度から選ぶ(専門実践教育訓練給付金など)
養成講座を選ぶ際には、費用と給付金制度を理解したうえで選択することが大切です。
キャリアコンサルタント養成講座は25万〜40万円台の費用が必要になる場合があり、経済的な負担を考慮しながら学習計画を立てる必要があります。
厚生労働省が実施する専門実践教育訓練給付金制度では、指定された講座を修了し受給条件を満たすことで、受講料の最大80%(50%が基本、さらに資格取得等で追加支給。年間上限40万円)が補助され、経済的負担を大きく減らすことが可能です。
講座選びでは費用だけでなく、給付金の対象講座かどうかを確認し、長期的な投資として適切な判断が求められます。
実績・合格率から選ぶ
養成講座を選ぶ際には、合格率や過去の実績を確認することが学習の安心につながります。
講座によって指導方法やカリキュラムの質に差があるため、合格率が高い講座は体系化された学習環境と確かなサポートを提供している傾向があります。
特に実技試験(面接・論述)ではロールプレイ演習の質が合否に影響しやすく、演習量や指導の細かさが充実している講座がおすすめです。
公開されている合格率だけでなく、講師の指導方針や卒業生の声を確認すると、自分の学習スタイルに適した講座を選びやすくなります。
サポート体制と講師の質で選ぶ
講座選びでは、受講中のサポート体制と講師の質を重視することが学習継続に大きく影響します。キャリアコンサルタントの学習は理論理解と演習の両立が必要なので、疑問点をすぐに解消できる環境が大切です。
質問対応のスピードや面談のフィードバック方法が明確な講座ほど、安心して学習を進められます。また、講師の実務経験や指導歴は学習の質に直結し、具体的な相談例を交えながら学べる講師は理解を深める力になります。
サポート体制と講師力が整った講座を選ぶことで、不安を感じずに学習を続けられるでしょう。
通学・通信など学習スタイルで選ぶ
学習スタイルは講座選びを左右する大きな要素で、通学か通信かによって学習の進め方が変わります。
通学制は講師や受講生と直接かかわりながら学べるため、実技試験(面接・論述)の質が高く、実技試験への実践的な準備を進めやすいです。
一方、通信制は自分の生活リズムに合わせて学習でき、時間の制約がある社会人や子育てと両立する人に適しています。
通信制でも対面演習が必須となる場合が多く、演習回数や参加形式を事前に確認する必要があります。
どちらのスタイルが自分の生活に無理が生じないかを検討すると、継続しやすい学習環境を整えられます。
\講座を比較して選ぼう!/
キャリアコンサルタントの講座を資料請求(無料)資格登録制度と更新制度について
キャリアコンサルタント試験に合格しただけでは、キャリアコンサルタントと名乗って活動することはできません。国家資格として名称を使用するためには、キャリアコンサルタント名簿への登録手続きが必須です。
ここでは、登録に必要な書類や費用、登録によって可能になる活動内容、そして五年ごとの更新制度と受講すべき講習の種類について詳しく解説します。
登録に必要な書類・費用
キャリアコンサルタント試験に合格した後は、キャリアコンサルティング協議会が運営する登録センターで登録申請をおこないます。登録申請は以下の2つです。
- - Web上のマイページから申請する
- - 郵送で申請する
Web申請はオンラインで手続きが完結し、郵送に比べて時間的・手続き面で効率的に進められます。
登録申請に必要な書類は、合格証のコピー(Web申請ではPDF形式でアップロード)、本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカードなどの画像データ)、および申請書類一式です。郵送申請の場合は、これらの書類をコピーして所定の封筒で送付します。
登録にかかる費用は、登録手数料8,000円と登録免許税9,000円の合計17,000円です。ファイル形式やサイズの詳細は登録センターの案内を参照してください。
登録するとできるようになること
キャリアコンサルタント名簿に登録すると、職業能力開発促進法によって保護された「キャリアコンサルタント」という名称を使用可能です。
これは名称独占資格としての権利であり、登録していない者がキャリアコンサルタントや紛らわしい名称を使用することは法律で禁止されています。
名刺や履歴書、職務経歴書に「国家資格キャリアコンサルタント」や「キャリアコンサルタント(登録番号〇〇〇〇〇)」と記載でき、専門性を客観的に証明できます。
企業の人事部門や人材紹介会社、教育機関などでキャリア支援業務に従事する際、登録済みの資格保有者であることが応募条件や優遇条件になるケースも多くあります。
5年ごとの更新頻度・講習の種類
キャリアコンサルタントの登録は5年ごとに更新が必要です。
更新をおこなわなければ登録が失効し、キャリアコンサルタントの名称を使用できなくなります。
更新制度は、資格保有者が常に最新の知識と技能を維持し、質の高いキャリアコンサルティングを提供するために設けられています。
| 区分 | 必要時間 | 主な内容 |
| 知識講習 | 8時間以上 | ・法律制度 ・労働市場 ・キャリア理論など |
| 技能講習 | 30時間以上 | ・ロールプレイ ・事例検討 ・スーパービジョン |
講習の内容やテーマは多岐にわたり企業内キャリア支援や若年者支援、中高年支援、メンタルヘルス、多様性への対応など、関心や専門分野に応じて選択できます。
\講座を比較して選ぼう!/
キャリアコンサルタントの講座を資料請求(無料)まとめ|キャリアコンサルタントになる第一歩を踏み出そう
キャリアコンサルタントを目指す過程では受験資格の確認、養成講座の修了、国家試験の合格、登録の手続きを理解することで迷わずに学習を進められます。
資格取得後には企業や教育機関、公共支援機関など幅広い領域で活躍でき、将来の働き方を柔軟に選択できます。
講座選びでは費用や合格実績、サポート体制、学習スタイルを慎重に比較することが大切です。
学習の第一歩を踏み出すことで専門性が高まり、相談支援の現場で充実したキャリアを築けるようになります。
キャリアコンサルタントの講座選びなら(BrushUP学び)


BrushUP学びはスクールや学校、講座の総合情報サイト。
最安・最短講座や開講日程、分割払いなどをエリアごとに比較して無料でまとめて資料請求できます。
まずは近くのスクールをチェックしてみてくださいね♪
電話での請求も可能です。
\講座を比較して選ぼう!/
キャリアコンサルタントの講座を資料請求(無料)- キャリアコンサルタント試験情報
- キャリアコンサルタント試験 試験内容を徹底解説 キャリアコンサルタント試験の難易度・合格率は? キャリアコンサルタント学科試験とは? キャリアコンサルタント試験の申し込み期間はいつ? キャリアコンサルタント試験の試験日程一覧 キャリアコンサルタント受験資格を徹底比較 キャリアコンサルタント実技試験とは? キャリアコンサルタント論述試験の内容は? キャリアコンサルタント技能検定2級とは? キャリアコンサルタント試験 出題内容・勉強法を徹底解説!
- キャリアコンサルタントを目指す方向けのおすすめ記事
- キャリアコンサルタントの年収は? キャリアコンサルタントの将来性は高い!? キャリアコンサルタントの仕事内容は? キャリアコンサルタント資格とは? キャリアコンサルタントは独学で合格できる? キャリアコンサルタント国家資格とは? キャリアコンサルタントになるには? キャリアコンサルタントの取り方決定版 キャリアコンサルタントの役割とは? キャリアコンサルティングとは? 本当にキャリアコンサルタントの資格は無駄? キャリアコンサルタントは副業にできる? キャリアコンサルタント資格の種類や活かし方
- キャリアコンサルタント養成講座の解説
- キャリアコンサルタント養成講座とは? キャリアコンサルタント養成講座はオンラインでも学べる? キャリアコンサルタント養成講座を辞めたい… キャリアコンサルタント講座のスクール一覧 キャリアコンサルタント養成講座をお得に受けるには? 働きながらキャリアコンサルタントを目指す! 土日開講のキャリアコンサルタント養成講座
- 【エリア別】キャリアコンサルタント養成講座を探す
- 東京都内のおすすめスクール 大阪府のおすすめスクール 北海道のおすすめスクール 愛知県のおすすめスクール 福岡県のおすすめスクール 埼玉県のおすすめスクール 京都府のおすすめスクール 静岡県のおすすめスクール 兵庫県のおすすめスクール 千葉県のおすすめスクール 島根県のおすすめスクール 石川県のおすすめスクール 長野県のおすすめスクール 岐阜県のおすすめスクール 岡山県のおすすめスクール 三重県のおすすめスクール 広島県のおすすめスクール 神奈川県のおすすめスクール 熊本県のおすすめスクール 鹿児島県のおすすめスクール 新潟県のおすすめスクール 香川県のおすすめスクール 岩手県のおすすめスクール 山形県のおすすめスクール 沖縄県のおすすめスクール 福島県のおすすめスクール 山梨県のおすすめスクール 群馬県のおすすめスクール 栃木県のおすすめスクール 茨城県のおすすめスクール 富山県のおすすめスクール 宮城県のおすすめスクール
- 【スクール別】キャリアコンサルタント養成講座を探す
- ヒューマンアカデミーの学校情報 資格の総合スクール LEC(れっく)東京リーガルマインドの学校情報 キャリア開発のパイオニア/日本マンパワーの学校情報 リカレントの学校情報 一般社団法人 日本産業カウンセラー協会の学校情報 一般社団法人 地域連携プラットフォームの学校情報 東海道シグマの学校情報 キャリアカウンセリング協会/GCDF-Japanの学校情報
- キャリアコンサルタント関連資格の記事
- 経営コンサルタント資格は本当に必要?
- キャリアコンサルタントとは?
- > キャリアコンサルタントになるには?国家資格取得までの4ステップを紹介