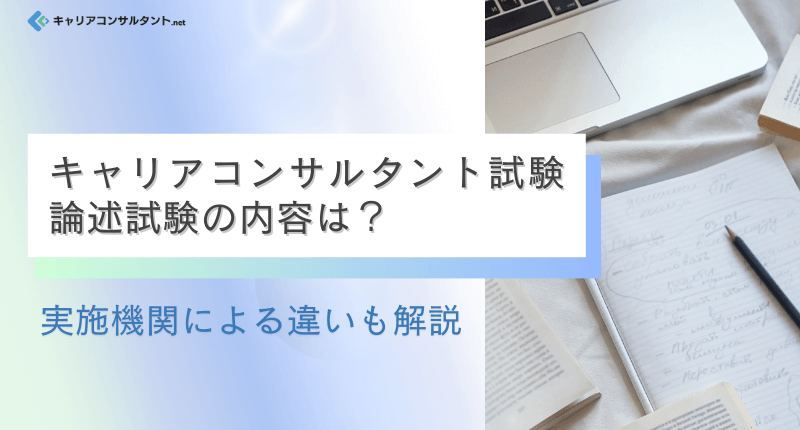
- キャリアコンサルタントとは?
- > キャリアコンサルタント試験
- > 【キャリアコンサルタント試験】論述試験の内容は?実施機関による違いも解説
【キャリアコンサルタント試験】論述試験の内容は?実施機関による違いも解説
更新日: 2025/11/26
キャリアコンサルタント試験の論述試験について、「どんな問題が出題されるのかな?」「どうやって勉強したらいいのだろう?」と悩んでいる方に向けて、試験内容を解説します。
実施機関による試験内容の違いについてもご紹介しますので、これから試験を受ける方も、受験を考えている方もぜひ参考にしてみてください。
\講座を比較して選ぼう!/
キャリアコンサルタントの講座を資料請求(無料)論述試験の内容は?
試験の概要
キャリアコンサルタント試験は、学科試験と実技試験(論述及び面接)で構成されています。論述試験の概要は次の通りです。尚、出題される試験内容は実施団体ごとに異なります。
| 論述 | 出題形式 | 記述式解答 |
| 論述 | 試験時間 | 50分 |
合格基準
実技試験は、論述と面接の合計点で合否が判断されます。実施団体ごとの合格基準は次の通りです。
| キャリアコンサルティング協議会 | ●150点満点のうち90点以上の得点 ●論述試験の満点の40%以上の得点 ●面接試験の評価区分「態度」「展開」「自己評価」のいずれにおいても満点の40%以上の得点 |
| 日本キャリア開発協会 | ●150点満点のうち90点以上の得点 ●論述試験の満点の40%以上の得点 ●面接試験の評価区分「主訴・問題の把握」「具体的展開」「傾聴」のいずれにおいても満点の40%以上の得点 |
論述試験のみに関しては、どちらの団体でも40パーセント以上の得点が必要です。論述試験は50点満点なので、20点の得点が必須ということになります。
過去問
論述試験の直近3回分の過去問は、実施団体のホームページで確認できます。誰でも無料でダウンロードできるので、興味のある方はぜひ入手してみてください。
ただし、論述試験の解答や解説は非公開となっています。また、最新の試験が実施されると、古い試験から順番に非公開となってしまいます。尚、論述試験の過去問は一般に販売されていません。
過去問の解答や詳しい解説について知りたい場合は、養成機関などで開講されている試験対策講座に参加するのも一つの手です。プロの講師から詳しい指導を受けられます。
\講座を比較して選ぼう!/
キャリアコンサルタントの講座を資料請求(無料)実施機関による違いは?
実施機関ごとの論述試験の違いについてまとめました。
資料の出し方
論述試験の内容は、キャリアカウンセリングの事例に関する資料を読んで、設問に答えるという構成です。提示される資料の出し方は、実施機関ごとに特色があります。
キャリアコンサルティング協議会
コンサルティングの内容がまとめられた事例記録が掲載されます。
事例記録の例
| 相談者情報: 名前、性別、年齢、略歴、家族構成といった情報。 |
| 面接日時: ●年●月 ●回目の面談といった情報。 |
| 相談の概要 |
| 相談者とキャリアコンサルタントの発言内容: 相談者が話した内容やキャリアコンサルタントの応答がまとめられている。 |
| 所感: キャリアコンサルタントの見立て・今後の方針 |
尚、事例記録には省略や空白になっている箇所があります。このような資料を読んで、設問に答えるスタイルです。
日本キャリア開発協会
キャリアコンサルタントと相談者のやりとりを書き起こした逐語記録が掲載されます。
逐語記録の例
| 相談者1(以下、CL):今の仕事がしっくりこなくて相談にきました。 キャリアコンサルタント1(以下、CCt ):今の仕事にしっくりきていないんですね。どういうことでしょうか。 CL2:そうなんです。今、仕事で●●の事業を担当しているのですが…(以下略) |
このように会話形式の資料を読んで、設問に答えるスタイルです。
また、逐語記録は【事例の前半(共通部分)】の後の展開を示した、【後半A】【後半B】の2パターンの資料が提示されます。
設問の主な内容
それぞれの実施機関で、どのような内容が問われているかご紹介します。尚、設問内容の詳細は実施試験によって異なるため、最新の試験傾向を知りたい方は実際の過去問を見てみてください。
キャリアコンサルティング協議会
設問の例として、次のような内容が問われています。
- 事例記録をもとに相談の概要をまとめる。
- キャリアコンサルタントの応答内容の意図を答える。
- 相談者の問題及びその根拠について具体的に記述する。
- 今後の方針を設定する。
キャリアコンサルティング協議会の出題は、システマティック・アプローチを重視していると考えられています。キャリアコンサルティングの全体フレームを理解しているかどうかは、資料の読み取りや設問の解答にも影響するため、意識したいポイントです。
日本キャリア開発協会
- 逐語記録の【後半A】【後半B】の対応の違いについて指定語句を用いて答える。
- 相談者の問題及びその根拠について具体的に記述する。
- 今後の方針を設定する。
日本キャリア開発協会の出題の特徴は、2パターンの面談内容を対比したスタイルということです。また、指定語句を用いて2つの事例を説明させる問題があります。指定語句の使い方をある程度押さえておくと解答しやすくなるでしょう。
解答量
どちらの実施団体でも全体的な解答量に大きな違いはありません。記述欄はマス目ではなく横書きの罫線となっています。
尚、設問ごとに指定されている解答行数は異なります。6行分指定されている場合は、6行に合わせて記述することを作問者側は意図しています。問われている内容を過不足なく答えられるように練習しましょう。
\講座を比較して選ぼう!/
キャリアコンサルタントの講座を資料請求(無料)解答のコツは?
全体の流れと必要なスキルを理解する
前述したシステマティック・アプローチのように、キャリアコンサルティングを行う際には、基盤となるカウンセリング理論や技法があります。
論述試験で用いられる事例記述や逐語記録も、そういった理論や技法が駆使されているため、まずはカウンセリングに必要な基本的な知識・スキルを身につけることが大切です。
キャリアコンサルティングのプロセスを理解した上で、「この設問は、プロセスのどの段階について問われているのか」を意識すると、解答すべき内容が整理できます。
また、キャリアコンサルタントの発言にも、目的や意図が隠されています。キャリアコンサルタントが行う質問には、相談者の漠然とした話の内容を明確にする機能や、相談者自身の自己理解を促す機能などがあります。このような点にも着目できるよう、まずは基本知識を身につけておくことが大前提となります。
汎用的な言い回しばかりにしない
過去問の中にも「具体的に記述せよ」という出題があるように、解答する際は汎用的な言い回しばかりにならないように注意が必要です。
「この問いにはこう答える」というテンプレートがあると解答しやすくなりますが、どんな問題にも対応できる文章では、内容が抽象的になってしまう恐れがあります。
そこで、事例記述や逐語記録に書かれている個別具体的な内容を記述に取り入れることで、より具体的な解答をするように意識しましょう。
実務においても、すべての面談がテンプレート通りに進むわけではありません。論述試験の際にも、相談者の個別性を踏まえて解答できるように、繰り返し練習することがおすすめです。
小手先のテクニックでは得点が難しい
論述試験の具体的な採点基準は公表されてはいませんが、出題者側の意図を理解して、説得力のある解答を記述することが大切です。付け焼刃的なテクニックでは解答欄を埋められたとしても、得点につながる答案にはならないかもしれません。
そこで、前述した通り、キャリアコンサルティングの基礎知識の習得や、カウンセリング内容に応じた柔軟な対応が求められます。漠然と論述問題を解くのではなく、これまでに習った知識やスキルと関連づけることで学習の質が高まります。
\講座を比較して選ぼう!/
キャリアコンサルタントの講座を資料請求(無料)論述試験の勉強方法は?
論述試験の採点基準は一般に公表されていないため、独学での学習が難しいと感じる方もいると思います。勉強方法のアイデアをご紹介するので、ぜひ参考にしてみてください。
参考書籍や解説書籍で解答方法を理解する
一般書籍の中にも、実技試験対策に関するものがあります。出題傾向や解答のポイントなどがわかるため独学での学習におすすめです。闇雲に論述問題の練習に取り組んでしまうと、非効率な学習になってしまいます。
論述試験は自由記述形式であるため「どう答えたらいいのか迷ってしまう」方もいると思います。解答方法のガイドラインとして、参考書籍から対応方法を学んでみましょう。
過去問や演習問題に取り組む
論述問題の対策には、実際に書いてみることが大切です。過去問や演習問題を活用して出題パターンに慣れましょう。時間内に文章を記述できるか、文量は過不足ないかなど、実際の試験の状況をイメージしてみてください。
そして、模範解答と自分の解答を比較して見直してみましょう。模範解答で用いられているキーワードや視点、文章の構成などにも着目して改善点を洗い出すことで、論述スキルを高められます。「ざっくりした要旨は同じだから正解だろう」と見過ごさず、解説と合わせて、解答をブラッシュアップさせましょう。
また、記述試験の基本として誤字脱字にも注意が必要です。最近はパソコンやスマートフォンを使うため、文字を書く習慣があまりない方もいると思います。試験では解答用紙に記述する形式のため、実際に手を動かして書く練習も忘れずに行いましょう。
試験対策講座を受講する
独学で勉強するとなると、「自分の解答は合っているのだろうか」「どのように改善していいかわからない」という悩みもあると思います。
自分の解答を客観的に評価してもらいたい方は、養成機関などで開催している試験対策講座の受講がおすすめです。プロの講師から添削してもらうことで、自分だけでは見落としてしまうポイントに気づくことができます。
試験対策の書籍は書店などで購入できるとはいえ、書籍の種類はあまり多くありません。「この問題の解説をもっと知りたい」というときに、講師へ質問ができると試験への不安も払拭できると思います。
\講座を比較して選ぼう!/
キャリアコンサルタントの講座を資料請求(無料)まとめ
論述試験に苦手意識や不安を感じている方も、出題内容を理解してしっかりと練習を重ねれば、合格に必要な力が着実に身につきます。
50点満点のうち20点の得点が合格ラインになるため、基礎を固めるだけでも十分に合格への道が開けます。自分の解答に自信がない方は、プロの講師による添削や指導が受けられる対策講座も活用してみてください。
\講座を比較して選ぼう!/
キャリアコンサルタントの講座を資料請求(無料)キャリアコンサルタントの講座選びなら(BrushUP学び)


BrushUP学びはスクールや学校、講座の総合情報サイト。
最安・最短講座や開講日程、分割払いなどをエリアごとに比較して無料でまとめて資料請求できます。
まずは近くのスクールをチェックしてみてくださいね♪
電話での請求も可能です。
\講座を比較して選ぼう!/
キャリアコンサルタントの講座を資料請求(無料)- キャリアコンサルタント試験情報
- キャリアコンサルタント試験 試験内容を徹底解説 キャリアコンサルタント試験の難易度・合格率は? キャリアコンサルタント学科試験とは? キャリアコンサルタント試験の申し込み期間はいつ? キャリアコンサルタント試験の試験日程一覧 キャリアコンサルタント受験資格を徹底比較 キャリアコンサルタント実技試験とは? キャリアコンサルタント論述試験の内容は? キャリアコンサルタント技能検定2級とは? キャリアコンサルタント試験 出題内容・勉強法を徹底解説!
- キャリアコンサルタントを目指す方向けのおすすめ記事
- キャリアコンサルタントの年収は? キャリアコンサルタントの将来性は高い!? キャリアコンサルタントの仕事内容は? キャリアコンサルタント資格とは? キャリアコンサルタントは独学で合格できる? キャリアコンサルタント国家資格とは? キャリアコンサルタントになるには? キャリアコンサルタントの取り方決定版 キャリアコンサルタントの役割とは? キャリアコンサルティングとは? 本当にキャリアコンサルタントの資格は無駄? キャリアコンサルタントは副業にできる? キャリアコンサルタント資格の種類や活かし方
- キャリアコンサルタント養成講座の解説
- キャリアコンサルタント養成講座とは? キャリアコンサルタント養成講座はオンラインでも学べる? キャリアコンサルタント養成講座を辞めたい… キャリアコンサルタント講座のスクール一覧 キャリアコンサルタント養成講座をお得に受けるには? 働きながらキャリアコンサルタントを目指す! 土日開講のキャリアコンサルタント養成講座
- 【エリア別】キャリアコンサルタント養成講座を探す
- 東京都内のおすすめスクール 大阪府のおすすめスクール 北海道のおすすめスクール 愛知県のおすすめスクール 福岡県のおすすめスクール 埼玉県のおすすめスクール 京都府のおすすめスクール 静岡県のおすすめスクール 兵庫県のおすすめスクール 千葉県のおすすめスクール 島根県のおすすめスクール 石川県のおすすめスクール 長野県のおすすめスクール 岐阜県のおすすめスクール 岡山県のおすすめスクール 三重県のおすすめスクール 広島県のおすすめスクール 神奈川県のおすすめスクール 熊本県のおすすめスクール 鹿児島県のおすすめスクール 新潟県のおすすめスクール 香川県のおすすめスクール 岩手県のおすすめスクール 山形県のおすすめスクール 沖縄県のおすすめスクール 福島県のおすすめスクール 山梨県のおすすめスクール 群馬県のおすすめスクール 栃木県のおすすめスクール 茨城県のおすすめスクール 富山県のおすすめスクール 宮城県のおすすめスクール
- 【スクール別】キャリアコンサルタント養成講座を探す
- ヒューマンアカデミーの学校情報 資格の総合スクール LEC(れっく)東京リーガルマインドの学校情報 キャリア開発のパイオニア/日本マンパワーの学校情報 リカレントの学校情報 一般社団法人 日本産業カウンセラー協会の学校情報 一般社団法人 地域連携プラットフォームの学校情報 東海道シグマの学校情報 キャリアカウンセリング協会/GCDF-Japanの学校情報
- キャリアコンサルタント関連資格の記事
- 経営コンサルタント資格は本当に必要?
- キャリアコンサルタントとは?
- > キャリアコンサルタント試験
- > 【キャリアコンサルタント試験】論述試験の内容は?実施機関による違いも解説